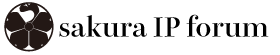代表的日本人を読む
人を尊び敬うことで、あのような人になりたいと思い芽生える向上心。それを導くきっかけとして、読書は大変有益な行為であることを実感している。本を読むことは、言い換えれば著者との出会いであり、また著作に記されている有名人や達人達との出会いであろう。この出会いによって人の心は突き動かされ、志気高くして己を磨く糧とする。
新渡戸稲造の『武士道』、岡倉天心の『茶の本』と並び三大日本人論に挙げられる内村鑑三の『代表的日本人』は、1894年に書かれたとされている。日本人に根付く精神性を、世界に紹介するために英字にて刊行された。のちに逆輸入されたものが邦訳され、現代においても名著の一つとして挙げられているようだ。西郷隆盛、上杉鷹山、中江藤樹、二宮尊徳、日蓮上人。日本を代表する歴史的偉人の足跡と性質を通して日本の文化を世に知らしめようとした本著は、日本人である私たちも、紐解き学ぶべきであろう。
本著に紹介されている諸先輩方において共通する点は、学問を極めて志を高く持ち、世間に求められ世に貢献した点であろう。学問においては、とりわけ陽明学が好まれ学ばれたことが色濃く伺える。儒教には、例えば四書の一つである『大学』に記されている「修身斉家治国平天下」という言葉には、以下のように端的に人徳修養の姿が描かれている。まず己の身を修めることで身の回りの人との関係が良好になる。その延長が、国を治め世に平和をもたらす。すなわち人徳は、己を修め才能を磨くことで備わるものであり、人徳極まれば世に求められ、そして世に益することで、己も周囲も含め皆が繁栄していく。このように、修身に端を発する善なる感化力が日本の文化には根付いており、徳育の実践が古来より多くの賢者達の間で実行されてきたことをうかがい知ることができる。日頃から、私が尊敬する諸先輩方について考えてみても、いわゆる「よくできた人」だと素直に感じるその根幹には、学問の力によって律された己があるのだろう。たとえその方が無学の学者であっても、既に備わっている人徳の上に成立することは、今となっては容易に推測できる。
私たちは日々学ぶ。学校に通い基礎的な普通教育を受け、教養を身に着ける。同時に情報処理技術をはじめとした、現代社会におけるリテラシーとしての実学を学ぶ。進学試験、就職試験ともに、たいていは学科試験があり、備わっている教養を試される。また面接試験においてはその人物性を問われる。世の中は多くの組織があり、それぞれに合った縁あるところへ属し、社会人として生活をする。そんな日々の生活の中で、私たちは時に悩み、そして時に喜びに浸りながら過ごす。このような情感は、多くの場合は家族や友人など他者と共感してともに過ごす。上記は、一般的な学校教育をベースとして成立している社会の在り方を私なりに考察したものである。
しかしながら、本著に描かれている諸氏の姿を見る限りにおいては、常に心が目的を見据え、日々の行いそのものは、敷かれているレールの上を行くようなイメージを抱く。私が感じている人生観とのギャップを認識する。 つまり、古より賢者と呼ばれる者の行動哲学には、一つの使命感を帯びてなされる、機先を制する行動を裏付ける自我を感じる。儒学をはじめとする諸学を学ぶ中で、己の心から湧き上がる智の泉を探し当て、それを情熱の源としているように感じる。情熱は志を抱き続ける原動力であり、それがあって賢者は足跡を刻んでいけるように感じる。学ぶことは知識を蓄えることの意味を持つ。そして同時に己の心を掘り下げて、新しい自己発見をもたらす側面があることを否定しきれない。
心に人生の指針を得ること。自我の覚醒。悟り。表現するに近い言葉は、思い返せばいくらでも出てくる。ただこれを実践することは容易ではないと思ってきた。「代表的日本人」に描かれている諸氏の生きている時代や境遇は、私たちが生きる現代社会よりはるかに厳しかっただろう。インターネットはなく、おそらく書物は貴重なものだったのだろう。このような逆境にも思える環境こそが、皆の向上心を育むバネとなり、気概を与え続けたのだろう。
内村鑑三が、明治維新の開国後50年も満たない激動の時代に、世界に日本を知らしめよう試み記された本書の息吹が、現代社会においては、どこに生き続けているのだろうか。今は見つけることができなくても、道徳を学びそれを頒布する諸氏に憧れ実践するものが一人でも増えたら、その者こそが真の学校を背負う賢者として世を担っていくのだろう。そしてその権利は誰にでもあるのだと、親しみをもって本著は読者に語りかけている気がする。
信じて真の学びを探すことにしよう。同時に心に芽吹く伊吹を求めることにしよう。いや、今私が抱いている探求心こそが、いま私の胸にある高揚感こそが、既に諸先輩方が体得された感覚と同じ類のものなのかもしれない。本著はすでに、私に何かを授けてくれたのだ。
masahiro_ohta
最新記事 by masahiro_ohta (全て見る)
- AfterEffectsショートカットキーOverView - 01/08/2020
- 「いいね」を購入につなげる 短パン社長の稼ぎ方 - 12/30/2019
- Robotic Process Automation Over view - 12/14/2019